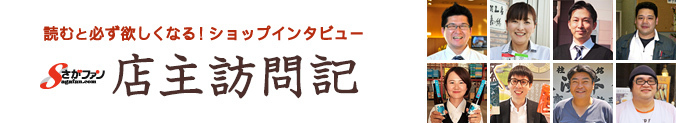2011年10月31日
竹八漬本舗 竹下八十さん

(株)竹八
代表取締役
竹下八十さん
漬物文化を伝えていくのが使命
食卓に漬物がある日常を再現したい
有明海近くの川副町。佐賀海苔をはじめ漁業、海産物加工業が盛んな町だ。その犬井道という地域にどこか懐かしく感じる建物がある。来年創業80周年を迎える「竹八漬」だ。歴史を感じさせる昔ながらのなまこ壁、かつて創業者・竹下八郎が大八車に有明の幸を乗せて売り歩いたであろうと感じさせる、時が止まったような細い道…。有明の珍味を酒粕漬けにし、その味は息子へ、そして孫へとじっくり伝えられた。「さがファン」オープン当初から参加いただいている漬物屋さんの老舗へ4年ぶり、2度目の訪問。
Q・前回の訪問から4年も経ってるんですね。そして来年創業80周年!何か変化はありましたか?
A・売上自体はあまり変わらないのですが、スタイルが変わってきています。ここ数年では、全体的に白米を食べる習慣が減っている傾向にあると思います。ごはんの横には漬物、それが日本の食卓の日常風景だったのですが、食文化は徐々に変化しているんでしょう。しかし、年を経て定年を迎え、余裕が出てきた層がまた漬物文化に戻り始めています。そのかわり、若い人は食べないという変化です。ごはんに漬物はもちろんですが、ゆっくり晩酌しながら漬物…そういったスタイルが増えてきて、新しいファンができはじめました。
Q・新しいファンができるなんてすばらしいですね。漬物が見直されてきたということでしょうか。
A・従来は各家庭の食卓に漬物が置いてあるのは当たり前だったのでしょうが、そうではなくなってきているので、ファンといってもにわかファンではなく、コアなファンが多いんですよ。特に、うちの漬物は有明海の幸を酒粕漬けにしているので、地方の特産物としておみやげに、と大量買いするお客様が多いんですね。そして、そのお客様が近所の方に配って…すると、どんどん口コミで広がってファンの村みたいなものが全国にできているんですよ!ですので、リピーターさんも増え、そしてまた大量買いをされる、という動きがここ数年ではありました。
Q・自分が美味しいと思ったものは、周りに伝えたいからでしょうね。漬物ファンの周りには漬物ファンがいると。4月の大創業祭は盛況だったようですね。
A・奈良漬体験コーナーは大変好評をいただいたので、7月にももう一度やったんですよ。面白いことに、若い層から人気だったのでやってみるものだなあと。奈良漬けは佐賀地方の漬物ではありませんが、創業者の祖父時代から、大和町の農家さんから瓜を提供していただいています。多分、九州で一番漬けているんじゃないかというぐらい年季が入っている商品です。大創業祭は5年前から開催しているのですが、漬物を売ろうというより、「竹八漬」の存在を知ってほしい、という思いから始めました。試食もOKで量り売りもします。普段は佐賀駅など土産物店に商品を置いてもらっていて、一般のお客様と触れ合うきっかけがあまりないものですので、大創業祭は直接、お客様と触れ合う貴重な機会です。来年は創業80周年なので、何かもっと新しいことをしたいですね。お米メーカーやお酒メーカーとタイアップして何かできないかな、とも考えています。
Q・漬物は定食屋さんに行ったら必ず出ますし、若い人になじみがないわけじゃないと思うんです。ただ、本当に美味しい漬物に出合ってないだけかと思うんですが…。
A・うちの漬物も竹下家の味が元ですからね。私の祖父から受け継がれてきた家庭の味です。それぞれの家庭での漬物の味っていうのはあると思うんです。実店舗では酒粕のみの販売も行っています。お客様から漬け方を聞かれたら秘密なしにお応えしますよ(笑)。でも、竹下家では酒粕、塩加減のブレンド、素材の下味つけなどは独特なので、「竹八漬」と全く同じものが各ご家庭で出来上がることはないとは思いますが。要は家庭の食卓に漬物があるか、ということですよね。
Q・やはり、家庭で漬ける人は少なくなってきてますね。だからこそ、美味しい漬物に出合ったらそこの漬物を何度も買うっていう状況が起きているのでは?
A・うちの看板商品でもある「真がに漬」がいい例ですね。がに漬けは佐賀・有明海特有の漬物です。海産物を漬物にする会社は、うちとは別に佐賀には数社あります。がに漬けは塩としょうゆで漬けることが多いのですが、うちの「真がに漬」は塩のみで漬けています。ですのでピリッと辛いんですよ。また「あら」と「つぶし」と2種類ありまして、食感をそれぞれお好みで楽しんでいただくようにしています。ジャリジャリとした食感が苦手な方のために、今「ねり」という、カニの甲羅を全部すりつぶし、ペースト状にした種類のがに漬の販売を考え中です。がに漬けは、佐賀特有の珍味で漬物なので隣県福岡、また東京でも「何これ?食べ方がわからない」と言われることが多いんですよ。でも一度、食べ方を覚えていただくと……何度も買っていただけるんですよね(笑)。
Q・そこでコアなファンが増えていくというわけですね。でも存在を知らない人も多いと思うんです。でも、漬物は元来日常的なものであって、特別感はないと思うのですが…。
A・はい。その通りです。漬物は日本の食文化のひとつです。最近は、スーパーなどで売っている簡単な浅漬けの元を使ったものを“漬物”と思っている若い世代も多いようですが、本当の漬物とは家庭の味で、食文化なんです。全国各地、気軽に定食屋さんに行っても、ホテルのレストランで和食のコースを頼んでも、必ず、なにがしかの漬物が箸休めとして出てきます。私たちの使命は、漬物文化を伝えていくこと。私が父、そして父が祖父に伝えられてきたように。竹下家では常に食卓に、漬物があったので違和感はまったくなく、今、私と弟の2人で自社の地下タンクで「竹八漬」をつくっています。もちろん、私の子ども世代にも伝えていきたいと常に食卓に漬物は欠かしていません。
Q・「竹八漬」さんは有明の幸、そして酒粕を熟成させて佐賀、有明海、川副町発信の漬物を作り上げているわけですが、今後の展開予定を教えてください。
A・地域特産物としてのPRはもちろん、珍味的な要素も含んでいるので、食べ方のアドバイスなどもいろんな形でしていきたいですね。京都の西京漬けのように、魚の酒粕漬けも徐々に好評価をいただいています。酒粕漬けは発酵食品ですので、漬けたてと時間がたってでは味も変わってきます。その味の違いをどう楽しむかもPRしたいですね。また健康にも良いということもPRしたいです。ネットショップ「さがファン」含め、イベントなどでも積極的に、「竹八漬」の良さをアピールしていきたいと思っています。そして各家庭の食卓に、本物の漬物が並ぶ日常を再現することに一役買えたら、と思っています!


酒粕は生き物。自社地下タンクで酒粕を熟成させ、その後素材と合わせ漬け込む。季節によって酒粕の熟成期間は1カ月~約3カ月と変わるが、常に安定した味を供給している。
良い酒粕は最初白色をしていて、ピンク色へと変わる。ダメな酒粕は赤くなり、やがて黒っぽくなる。タンクから美しいピンク色で出す酒粕…そこが狙い時だ。
 |
 |
 |
川副町の本店よりも、佐賀駅や土産物センターの方が商品は充実しているが、雰囲気がある本店に訪れるのもまた一興。タイムスリップしたような感覚が味わえる、「竹八漬」の本店の白壁、なまこ壁が歴史を物語る。


地下タンクがある自社も創業80年を迎えるにふさわしい雰囲気で町内にドンと構えている。

自社内のロビーには立派な看板が。歴史を感じさせる重厚なシンボルだ。