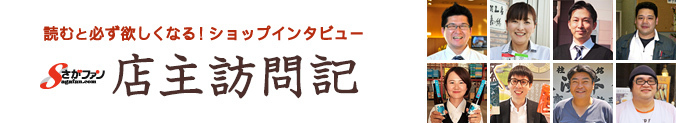2014年01月31日
「竹八漬本舗」竹下 八十さん

(株)竹八
代表取締役
竹下 八十さん
漬物文化に新たなる可能性が輝く!
珍味業界初の商品「キューブ」が新登場!
日本人のソウルフードといえば、米、味噌汁―そして漬物。しかし、時代の変化に伴い、食卓から漬物が消えゆこうとしている。そんな中、今年創業82周年、老舗の看板を守りながら、新たな挑戦を試み続ける「竹八漬本舗」さん。祖父から父へ、父から孫へ伝えられた、ふるさとの文化がギュッと詰まった有明珍味の粕漬。伝統の味を変えずにどう新たなファン層をつかむのか…? 約2年ぶり、若き社長の熱い想いを伺った。
Q・最近、珍味業界初の画期的な商品「キューブ」が新登場したらしいですね!
A・漬物をとりまく状況はここ2年でも変化しています。元々、漬物は家庭の味で食卓には必ずあるもので、白米と共にいただくものでしたが、現在は晩酌のお供というスタイルが多いですね。しかし、定食屋さんに行けば必ず漬物はついてきますし、決してなじみが薄くなっていっているモノでもないんですよ。ただ、私たちがつくる漬物は有明海の海幸の粕漬で、全国的に見れば珍味にあたるんだということに気付きました。珍味って最初食べるのに勇気が要りますよね。そこで思いついたのがこの商品なんです。
Q・確かに。食べ慣れた人にとっては当たり前ですが、特に若い人などにはなじみがありませんね。
A・定食屋で出てくるたくわんや高菜が漬物、という認識だと思います。ですので、まず手にとって食べてもらうことを目的として、見た目もかわいらしく、手頃な値段でちょっとづつ竹八漬の漬物を味わっていただく「キューブ」として商品化したんです。うちの子どもはご飯と一緒に粕漬を平気で食べますけど(笑)、粕漬を食卓に置いている方ってほとんど年輩者なんですよね。佐賀の地酒も最近、見直され人気が高まっています。晩酌のお供からでも手軽に楽しんでいただきたい、という想いでやっと商品化にいたりました。
Q・これはカワイイですよね。ギフトにもぴったりだし、女性受けも良さそうです!
A・でも、ここまでくるのに大変だったんですよ。まず箱探しが難航しました。どの食品もですが、小さい商品は手間がかかるし利益が出ません。お得感からすれば、通常の商品をお薦めしますよ。でもこの小ささ、50gというところがポイントなんです。ラベルにも全種類、有明海をモチーフに波の模様を入れ、9個入りのギフトボックスも少し高級感を出しました。去年の春に商品化し、お歳暮の時期にギフトボックスをつくったばかりです。
Q・一つ買いももちろん、ギフトでは4個、6個入りもあるんですよね。
A・どのギフトセットも、相手の好みに合わせて組み合わせることができます。九州では博多阪急、関東の百貨店では反応が良いようですね。特に関東では粕漬になじみがないので、こういった見た目にインパクトがある商品から入っていただき、次につながっていければいいなあ、と思っています。今度、東京の伊勢丹で一週間イベントがあるのですが、そこでどう反応が出るのかが楽しみです。
Q・今はギフト寄りですが、コンビニとかにちょっと置いていても手軽に買っていけそうですね。どう展開していく予定ですか?
A・「キューブ」は一般のお客様から見たら面白い商品なのですが、これを商品化しようとした時に、売れるわけがない、利益が出ない!と周りからいろいろ指摘を受けたんですよ。難航して見つけた小さい箱代が思った以上に高く、また、中の商品がもれないようにフタと箱の間に透明なフィルムを貼っているんですが、その機械の導入にも費用がかかりました。今まで、賞味期限切れで食べきれずに捨ててしまう、という課題が漬物にはあったのですが、その課題はクリアできても、今のところ決して利益の出る商品ではありませんね。
Q・しかし、可能性は広がりますね!「手にとって食べてもらうきっかけ」と「食べきりサイズの気軽さ」の実現と今までには全くなかった商品です。
A・そうですね。だから今後の課題は流通になってくると思います。ここ数年、コンビニで食べきりサイズのおかずが小分けパックで売られて売上が急上昇しているなど、個食にスポットが当たっていますよね。魚の切り身なんかもレンジでチンするだけで食べられる…以前は考えもしなかったことです。それだけ時代が変わり、人々の需要も変わってきています。「キューブ」は個食という状況にもぴったりマッチするので、ターゲットを個食に向けることもできますが、販売する店が同じ想いを持っておかないと難しいですね。
Q・なかなか、商売としては売り方が難しい商品なんですね…。
A・例えばギフトボックスだと、全商品賞味期限が違いますからね。また粕漬は基本、冷凍はせず冷蔵保存です。酒粕は生き物ですから、外気との温度変化で色がすぐに変わってしまうんですよ。だから冷凍保存ができないんです。うちから直接発送する商品と、一度店に卸す商品とではタイムラグが出てきてしまいます。お客様には食べきれずに捨ててしまわず、一番ベストな状態の粕漬を味わっていただくのが最大の目的ですので、各販売店の売り方…冷蔵庫の形から始まり、ディスプレイの仕方など課題は盛りだくさんですよ。
Q・どの業界でも老舗が危機的な状況にあります。個人企業であるに関わらず、代々受け継いだ暖簾を守りながら新アイデアで未来を切り拓いていく…素晴らしいですね!
A・とにかく美味しいんですよ、うちの粕漬(笑)。やっぱり、自分が子供のころから親しんできた習慣を途絶えさせたくないですからね。そして、それがふるさとの文化ですから、それを子ども世代に伝えていくのが使命だと思っています。でも、今まで通りでは良いものも伝わりませんから、伝える方法を常に考えているというだけなんですけどね。だから、あっちこっち見学を理由にふらついていて時には変な人になっていますよ、私(笑)。今後、居酒屋やレストランなど飲食店の小鉢にうちの粕漬を進出させたいですね。やっぱり私一人だと限界がありますから、有明海の漬物業界全体のことを考えると、同業他社との連携も必要になってくると思います。昔からのコアなファンを大事にしながら、新しいファン層を広げていくために、「さがファン」でもいろいろ展開していくので、ぜひ期待していてくださいね!



小さいながらも美味しさはそのまま。ギフトにも、一人晩酌にもピッタリな「キューブ」。小箱はしっかりとしたつくりで、食べた後も小物入れとして使う人も多いとか。


酒粕は生き物。自社地下タンクで酒粕を熟成させ、その後素材と合わせ漬け込む。季節によって酒粕の熟成期間は1カ月~約3カ月と変わるが、常に安定した味を供給している。
良い酒粕は最初白色をしていて、ピンク色へと変わる。ダメな酒粕は赤くなり、やがて黒っぽくなる。タンクから美しいピンク色で出す酒粕…そこが狙い時だ。
 |
 |
 |
川副町の本店よりも、佐賀駅や土産物センターの方が商品は充実しているが、雰囲気がある本店に訪れるのもまた一興。タイムスリップしたような感覚が味わえる、「竹八漬」の本店の白壁、なまこ壁が歴史を物語る。


地下タンクがある自社も創業82年を迎えるにふさわしい雰囲気で町内にドンと構えている。

自社内のロビーには立派な看板が。歴史を感じさせる重厚なシンボルだ。
2011年10月31日
竹八漬本舗 竹下八十さん

(株)竹八
代表取締役
竹下八十さん
漬物文化を伝えていくのが使命
食卓に漬物がある日常を再現したい
有明海近くの川副町。佐賀海苔をはじめ漁業、海産物加工業が盛んな町だ。その犬井道という地域にどこか懐かしく感じる建物がある。来年創業80周年を迎える「竹八漬」だ。歴史を感じさせる昔ながらのなまこ壁、かつて創業者・竹下八郎が大八車に有明の幸を乗せて売り歩いたであろうと感じさせる、時が止まったような細い道…。有明の珍味を酒粕漬けにし、その味は息子へ、そして孫へとじっくり伝えられた。「さがファン」オープン当初から参加いただいている漬物屋さんの老舗へ4年ぶり、2度目の訪問。
Q・前回の訪問から4年も経ってるんですね。そして来年創業80周年!何か変化はありましたか?
A・売上自体はあまり変わらないのですが、スタイルが変わってきています。ここ数年では、全体的に白米を食べる習慣が減っている傾向にあると思います。ごはんの横には漬物、それが日本の食卓の日常風景だったのですが、食文化は徐々に変化しているんでしょう。しかし、年を経て定年を迎え、余裕が出てきた層がまた漬物文化に戻り始めています。そのかわり、若い人は食べないという変化です。ごはんに漬物はもちろんですが、ゆっくり晩酌しながら漬物…そういったスタイルが増えてきて、新しいファンができはじめました。
Q・新しいファンができるなんてすばらしいですね。漬物が見直されてきたということでしょうか。
A・従来は各家庭の食卓に漬物が置いてあるのは当たり前だったのでしょうが、そうではなくなってきているので、ファンといってもにわかファンではなく、コアなファンが多いんですよ。特に、うちの漬物は有明海の幸を酒粕漬けにしているので、地方の特産物としておみやげに、と大量買いするお客様が多いんですね。そして、そのお客様が近所の方に配って…すると、どんどん口コミで広がってファンの村みたいなものが全国にできているんですよ!ですので、リピーターさんも増え、そしてまた大量買いをされる、という動きがここ数年ではありました。
Q・自分が美味しいと思ったものは、周りに伝えたいからでしょうね。漬物ファンの周りには漬物ファンがいると。4月の大創業祭は盛況だったようですね。
A・奈良漬体験コーナーは大変好評をいただいたので、7月にももう一度やったんですよ。面白いことに、若い層から人気だったのでやってみるものだなあと。奈良漬けは佐賀地方の漬物ではありませんが、創業者の祖父時代から、大和町の農家さんから瓜を提供していただいています。多分、九州で一番漬けているんじゃないかというぐらい年季が入っている商品です。大創業祭は5年前から開催しているのですが、漬物を売ろうというより、「竹八漬」の存在を知ってほしい、という思いから始めました。試食もOKで量り売りもします。普段は佐賀駅など土産物店に商品を置いてもらっていて、一般のお客様と触れ合うきっかけがあまりないものですので、大創業祭は直接、お客様と触れ合う貴重な機会です。来年は創業80周年なので、何かもっと新しいことをしたいですね。お米メーカーやお酒メーカーとタイアップして何かできないかな、とも考えています。
Q・漬物は定食屋さんに行ったら必ず出ますし、若い人になじみがないわけじゃないと思うんです。ただ、本当に美味しい漬物に出合ってないだけかと思うんですが…。
A・うちの漬物も竹下家の味が元ですからね。私の祖父から受け継がれてきた家庭の味です。それぞれの家庭での漬物の味っていうのはあると思うんです。実店舗では酒粕のみの販売も行っています。お客様から漬け方を聞かれたら秘密なしにお応えしますよ(笑)。でも、竹下家では酒粕、塩加減のブレンド、素材の下味つけなどは独特なので、「竹八漬」と全く同じものが各ご家庭で出来上がることはないとは思いますが。要は家庭の食卓に漬物があるか、ということですよね。
Q・やはり、家庭で漬ける人は少なくなってきてますね。だからこそ、美味しい漬物に出合ったらそこの漬物を何度も買うっていう状況が起きているのでは?
A・うちの看板商品でもある「真がに漬」がいい例ですね。がに漬けは佐賀・有明海特有の漬物です。海産物を漬物にする会社は、うちとは別に佐賀には数社あります。がに漬けは塩としょうゆで漬けることが多いのですが、うちの「真がに漬」は塩のみで漬けています。ですのでピリッと辛いんですよ。また「あら」と「つぶし」と2種類ありまして、食感をそれぞれお好みで楽しんでいただくようにしています。ジャリジャリとした食感が苦手な方のために、今「ねり」という、カニの甲羅を全部すりつぶし、ペースト状にした種類のがに漬の販売を考え中です。がに漬けは、佐賀特有の珍味で漬物なので隣県福岡、また東京でも「何これ?食べ方がわからない」と言われることが多いんですよ。でも一度、食べ方を覚えていただくと……何度も買っていただけるんですよね(笑)。
Q・そこでコアなファンが増えていくというわけですね。でも存在を知らない人も多いと思うんです。でも、漬物は元来日常的なものであって、特別感はないと思うのですが…。
A・はい。その通りです。漬物は日本の食文化のひとつです。最近は、スーパーなどで売っている簡単な浅漬けの元を使ったものを“漬物”と思っている若い世代も多いようですが、本当の漬物とは家庭の味で、食文化なんです。全国各地、気軽に定食屋さんに行っても、ホテルのレストランで和食のコースを頼んでも、必ず、なにがしかの漬物が箸休めとして出てきます。私たちの使命は、漬物文化を伝えていくこと。私が父、そして父が祖父に伝えられてきたように。竹下家では常に食卓に、漬物があったので違和感はまったくなく、今、私と弟の2人で自社の地下タンクで「竹八漬」をつくっています。もちろん、私の子ども世代にも伝えていきたいと常に食卓に漬物は欠かしていません。
Q・「竹八漬」さんは有明の幸、そして酒粕を熟成させて佐賀、有明海、川副町発信の漬物を作り上げているわけですが、今後の展開予定を教えてください。
A・地域特産物としてのPRはもちろん、珍味的な要素も含んでいるので、食べ方のアドバイスなどもいろんな形でしていきたいですね。京都の西京漬けのように、魚の酒粕漬けも徐々に好評価をいただいています。酒粕漬けは発酵食品ですので、漬けたてと時間がたってでは味も変わってきます。その味の違いをどう楽しむかもPRしたいですね。また健康にも良いということもPRしたいです。ネットショップ「さがファン」含め、イベントなどでも積極的に、「竹八漬」の良さをアピールしていきたいと思っています。そして各家庭の食卓に、本物の漬物が並ぶ日常を再現することに一役買えたら、と思っています!


酒粕は生き物。自社地下タンクで酒粕を熟成させ、その後素材と合わせ漬け込む。季節によって酒粕の熟成期間は1カ月~約3カ月と変わるが、常に安定した味を供給している。
良い酒粕は最初白色をしていて、ピンク色へと変わる。ダメな酒粕は赤くなり、やがて黒っぽくなる。タンクから美しいピンク色で出す酒粕…そこが狙い時だ。
 |
 |
 |
川副町の本店よりも、佐賀駅や土産物センターの方が商品は充実しているが、雰囲気がある本店に訪れるのもまた一興。タイムスリップしたような感覚が味わえる、「竹八漬」の本店の白壁、なまこ壁が歴史を物語る。


地下タンクがある自社も創業80年を迎えるにふさわしい雰囲気で町内にドンと構えている。

自社内のロビーには立派な看板が。歴史を感じさせる重厚なシンボルだ。
2007年10月31日
株式会社 竹八 代表取締役 竹下八十さん

株式会社 竹八
代表取締役・竹下八十さん
珍味であり、漬け物―粕漬けといえば「竹八漬」!
佐賀の"おみやげ"として定着させていきたい。
北の玄界灘、南の有明海―。性格のまったく異なる2つの海にいだかれた佐賀。日本最大の干拓地、有明海はいつも穏やかな波をたたえ、秋にはノリ漁業のためのノリヒビとよばれる竹の棒がズラリと並ぶ。その風景は年を越して春まで見られる風物詩となっている。豊穣の海と呼ばれる有明海の干満の差は最大約6m。稀少な泥のじゅうたんの中には、ムツゴロウを代表にさまざまな変わった生き物が生息し、昔は普通の家庭の食卓に有明海の幸が並んできた。現在こそ水揚げ量は減少したが、その味はしっかり守られ今でも生きている。創業75年、一人の男が作り上げた「竹八漬」。川副町の本社でお話を伺った。
Q・珍味の王様、たいらぎの貝柱を銘酒粕漬けにした「竹八漬」。歴史を教えてください。
A・私の祖父である、竹下八郎が17歳の時に作り上げた有明海珍味の漬物です。彼は昭和7年当時、個人商店を営む兄を手伝っていて、14.5歳のころからこの地・川副町で天秤棒を肩にかけて、朝、海産物を仕入れ、夕方、町に売りに出かけるという行商人をやっていたんですね。その頃は現在と違って海産物の水揚げ量も多量で、そしてもう一つ、今では焼酎が主流ですが、元々佐賀は米どころですので、日本酒が多かったんです。そこから出る酒粕も多量。あまったものは捨てざるを得ないという状況でした。そこで、彼は「どうせ余った海産物と酒粕を捨てるなら…」と海産物を粕漬けにすることを思いついたんです。
Q・海産物の漬け物、って珍しいですよね。漬け物といえば野菜等が多いのですが…。
A・漬け物っていろいろ種類がありますが、大体が塩漬けですよね。だけど当時は塩漬けだと保存できなかったんです。酒粕は発酵食品だったので保存食にもなりました。また酒粕は熟成すると旨みがジワジワと出てきて、元々塩っけがある海産物にマッチするんですよ。現在でも、海産物を漬け物にしているのはここと福岡・柳川ぐらいじゃないでしょうかね。"漬け物でもあり、珍味でもある"というところが大きな特徴です。
Q・創業75年、最初のころと味の違いはありますか?どのように作っているんですか?
A・製法は基本的に当時と変わっていません。「竹八漬」として売り出したのは昭和40年のころで、それ以前は「貝柱漬」として売っていました。戦争時は、祖母がコツコツ作り続けていたようです。現在は職人一人と助手、身内で作っています。一番重要なのは、酒粕の配合具合。これは見て覚える、という感覚しか頼るものはありませんね。だから、今は職人一人が伝統の味を守っていますが、ちょっとした配合の違いで味が変わったりします。また、酒粕は発酵して日々、生きていますから1日1日味は変わっていくんですよ。
Q・漬け物ができあがるまでどれくらい時間をかけるんですか?
A・季節によっても違います。まず酒粕を熟成させるんですが、冬場は約3ヶ月、夏場は温度の都合で約1ヶ月。それから冷蔵庫に保存し約2~3ヶ月おきます。冬場と夏場のものを同じ味にするためには、酒粕の配合やブレンドの仕方を変えたりしています。保存後は、貝柱と酒粕を機械で約30分ほど混ぜ、それから約1~2週間漬け込みます。そしてやっと出荷となるんです。
Q・漬け物の食べごろってあるんですか…?
A・これは好みによりますが…、漬けた最初のころって、あまり塩っけがにじみ出てこないんですよ。粕漬けは1日1日味も変わり、色も変わるんです。賞味期限は常温で90日間ですが、私がお薦めするのは、常温で1ヶ月ぐらいが食べごろのピークですね!
Q・有明海では現在水揚げ量が激減していますが、影響はどの程度ありますか?
A・ここが一番問題ですが…。作る分は簡単なんですが、買い付けが難しいんです。有明海では、現在ではほとんどノリ漁業が主になってしまいました。ノリ漁業の後にウミタケなどの仕入れを行うのですが、仕入れの状態が塩漬けされていたり、されていなかったりとバラバラ。ここ10年で、ノリ漁業もウミタケ漁も後継者が育たなくなってしまい、以前のようにきっちり同じ状態で、安定して仕入れることができなくなってしまったんです。
また、日本酒の酒粕も同じで現在、佐賀はすっかり焼酎派になってしまいました。酒蔵も激減し、酒粕が集まらない…そこで安定供給のために、銘酒を広島や京都から仕入れ、たいらぎにおいては輸入に頼らざるを得ない状況です。
Q・珍味であり、漬け物の「竹八漬」のおいしさはどこにあるんでしょうか?
A・ズバリ、酒粕ですね。もちろん素材も高品質ですが。祖父は何よりも酒粕にこだわったそうです。粕になる酒は吟醸に近い純米銘酒で何種類かブレンドし味を作っていきます。 酒粕は発酵食品だから、日々生きている。だからこそおいしいし、味が変わっていくのも面白いですよね。でもお客様の中にはずっと変わらない味を求める方も多いので、基本は味を変えないように作っています。でも、必ず変わっていきます。酒粕にはクセがなく、味がない食べ物が合います。貝柱はちょっと甘みがあって、適度な塩っけもあって、粕漬けにはピッタリですね。
Q・お客さんの反応はいかがですか…?
A・リピーターで年輩の方が多いです。やはり、食卓には必ず漬け物が置いてあった世代ですからね。また、全国各地で物産展に出品したり、こうやって「さがファン」で通信販売していますが、皆さん最初は「何これ?」から入るようです。珍味なの?漬け物なの?何物なの?って(笑)。でも、一回購入して試していただけるとハマっていただけるようでうれしいですね。私としては、若い方にこそ食べていただきたいです。ほかほかの白ごはんにかけるのもおいしいですが、お酒のつまみには本当にピッタリですから!
Q・漬け物の食べ方、漬け物の日常的な役割って何でしょう?
A・昔は食卓に各家庭で漬けた、漬け物があるのが当たり前でした。今はあまり見られない光景ですね。でもほかほかの白ごはんや、お酒のおつまみに、ひとつ加えるだけで、ごはんやお酒がより美味しくなる。佐賀で今ポピュラーな漬け物といえば、青高菜ですかね。
粕漬けになると、うちと、玄海灘の方で松浦漬、玄海漬というものがあります。有明海の珍味の代表的な漬け物は、うちでも売れ筋No.1の「真がに漬」。唐辛子をブレンドしたピリ辛でごはんにちょっとつけるだけ、お箸でちょっとなめるだけで、ごはんもお酒もいけます。でも人気なのに、クレームも一番多いんですよ。「食べ方がわからない!」って。普通の漬け物感覚でガバッと食べると、口から火吹きますからね(笑)。そこで最近、食べ方の説明書もつけました(笑)。
Q・今後「さがファン」で展開していきたいことってありますか?
A・やはり、まだ知名度が低いので、より多くの皆様に知っていただくようにアプローチしたいですね。物産展のときに、「さがファン」のアドレスを書いたちらしを配ったり…とかですね。また、うちではこれも珍味「わらすぼ」も売ってるんですよ。昔はこの辺りの各家庭の軒下でぶらさがっていたものでしたが、ずいぶん水揚げ量も減ってしまいました。
こちらもビールなどのおつまみにピッタリ。おいしい珍味がたくさんあって、おいしい食べ方がたくさんあるっていうことを、ネットを通じて伝えていきたいと思っています。
Q・これからの「竹八」さんの目標を教えてください。
A・時代は変わっていっていますが、私たちは75年伝統の味を守り続けてきました。昔は「粕漬け=竹八」と呼ばれたものです。先代の祖父が言っていたのは「商いはまごころ」。決して「有名だから買う」のではなく、「おいしいから買ったよ」と言われることを喜んでいました。昔、うちの漬け物を食べた人が「この味だ、変わっていない」と思い出してくれたらうれしいですね。そして、再び、「粕漬けといえば竹八漬」と言われるようになりたいです。そして、全国の人が佐賀に来た時に「佐賀にはこんな味があるんだ!」と発見してもらい、佐賀の特産品として認めていただけるようになれれば…。佐賀に来たから「竹八漬」を買って帰ろう…というように、佐賀のおみやげとして定着させていきたいなと思っています!

ロビーには立派な「竹八漬」の看板が。歴史を感じさせる重厚なシンボル。

佐賀市川副町にある「竹八」。町内には数社漬け物屋さんがある中で一番の老舗。

コツコツと職人の手で作り上げた伝統の味の数々。漬け物のある生活が始めたくなった取材だった。
>> 竹八漬けの商品はこちらからご購入いただけます。